アラブの世界、そこが知りたい! 人間関係の円滑剤、ユーモアのセンス!
アラブ人は、常に力を抜こうとする「弛緩志向」というマインドが得意。そして緊張を解消ためにも笑いやユーモアを生活によく取り入れるのだ。仕事など緊張のある一大事の時でもジョークを飛ばしたりユーモアのある表現を使うなどして気楽にしていられるのが「できる人」の証である。一方、日本人は、大切な場面になればますます力が抜けず表情も硬くなる「緊張志向」が目立つ。
アラブのトップリーダーや「できる人」は、どんなにせっぱ詰まった時でも、メンタルの強さや自信などを見せる証として冗談一つや二つ言えるゆとりをアピールする。
一方、日本人は、いつも力を入れて頑張っていなければならないのが美徳の一つだ。「生懸命やる」ことや「張り切る」ことはいいことで、力を抜くことは「不真面目」や「怠け」でよくないことである。そのため、日本では、冗談は真面目な姿勢に反するとの体育系的考えが支配
的である。そのためか、日本人にはあまりユーモアがないと思われているが 、日本には漫才や落語などの豊かなお笑い文化がある
人はみな同じように笑うが、同じことについて笑うとは限らない。とくに文化の異なる人同士ならば、なおさら笑いのツボは違う。

アラブ人はユーモアのセンスがあるとよく言われる。アラブ地域の多くの国でコメディ映画や演劇が氾濫している状況をみると、「やはりアラブ人はお笑い好きなんだな」とつくづく思う。
アラブでは、人柄をつくる要素のうちで一番高く評価されるものの一つは、ユーモアのセンスである。ユーモアはとても大切な資質とされ、他人とのコミュニケーションとその交友関係を深める重要な要素の一つとされている。多くの場合は、笑いを通して交流をはかるのが目的だが、つねに面白いことを言って周りの皆を笑わせるパワーをもつ人は、いつでも余裕を失わずに、分別のある判断ができる人と評価される。
アラブの映画には、ぎりぎりの切羽詰った状況に追い詰められた主人公が、ふと軽い冗談を言って、なんでもないような様子で周囲の予想を裏切る、そんなシーンがたびたびある。そういうことができる人こそ、まさしくユーモアのセンスのある人だとアラブ人は考える。
「真のユーモアリスト」とは、けたけた笑ってばかりでなく、真面目に感じながらもふざけて考え、冗談を言いながら真面目な顔を崩さずにいる人のことである。アラブの紳士は、物事が悪いほうに傾くと、たいていは苦笑いして、ボソリと痛烈なつぶやきを漏らす。そして、自分について笑うことはほとんどなく、他人を笑うことが多い。とにかく、苦しいとき、八方ふさがりのときほどユーモア精神が必要だ。苦虫をかみつぶしたような顔をしていたら、逆境を乗り越えられないし、よいアイディアも浮かばないだろう。
アラブの笑いには、風刺を含んだ痛烈なものが多く、複雑な言葉遊びや地口がしばしば用いられる。その対象となるのは、政府、女性、同国人の田舎者。アラブ人のジョークは、現実的で露骨だ。アラブでジョークを口にすることは、社交を円滑にするための「からかい」という色彩が濃い。言ってみれば、アラブ人のユーモアスタイルは、ウィットで軽快だ。
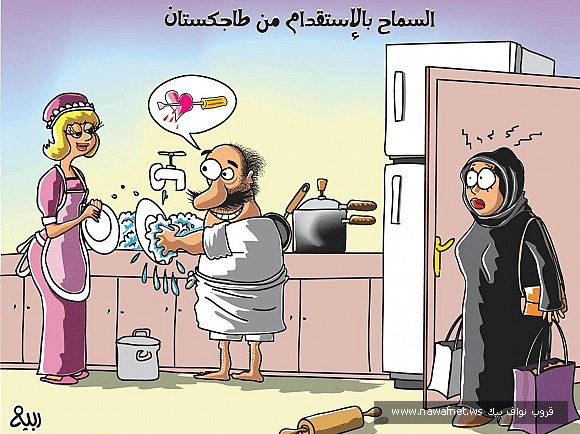
アラブの新聞の風刺画
国民の鏡である新聞にも、アラブのユーモアのセンスが生きている。アラブの新聞は、ユーモア精神や遊び心にあふれていて、一般記事や社説はともかく、コラムは「アイロニー表現を交えながら、ちょっぴり毒があり、それでいて上品さを失わない」「くすっと、もしくは、楽しく笑える」ユーモアでいっぱいだ。それは、アラブの新聞ならではの「言論の自由のスタイル」なのである。アラブ社会では、ユーモアはまさしく社会の大事な潤滑剤なのだ。
アラブでは、どんなに厳しい局面にあるときも、周りの人と交流をはかる手段として、ジョークを飛ばすセンスを身につけることが重要だとされる。ジョークはアラビア語で「ヌクタ」というが、このヌクタこそ人々の生活ぶりや感性を知るうえで貴重なものだ。
アラブでは、政治、経済などの社会的問題、毎日の日常的な出来事などを風刺した絵(風刺画)が今も昔と変わらず庶民から愛されている。
アラブのジョークの王道となるのは、エジプト・ジョークだ。政権や国際情勢を笑うものから田舎者をおちょくるものまで、バラエティーに富んでいて、たいへんおもしろいものがある。三つの例を載せよう。
ジョークその①
息子が母親のコンピュータを見ると、次のようなメールが届いていた。
「愛する妻へ、無事に着いた。インターネットで知らせを受け取れるなんて、驚くだろうね。
今はこっちにもコンピュータがある。だれでも家族や大切な人に、毎日の出来事を知らせることができるんだ。
まだ到着して1時間だけど、すべて準備は整っていると思う。あとは二日後に君が来るのを待つだけだ。
とても恋しいよ。会いたい。ぼくの旅と同じように、君の旅もスムーズにいくように祈っている。
ついでに。あまりたくさん服を持ってくる必要はないよ。ここの暑さはすごい、地獄さ!」
ジョークその②
先生 ― 「盗む」 の過去形は?
生徒 ― 「盗んだ」 です。
先生 ― よし。それでは未来形を言ってみろ。
生徒 ― 「刑務所」 です。
ジョークその③
女優A ― あら、あなたのご主人、新しい服を着てるのね。
女優B ― そうじゃないの。主人が新しいの
ジョークその④
一人の青年が書店の店員に尋ねてきた。
「『二週間で金持になる方法』という本をください」
「はい、どうぞ。ところでこの本の続編もあるのですが、いかがですか?」
「その本のタイトルは?」
「『刑法早わかり』です」
日本人とアラブ人のお互いのコミュニケーションの違いにより、ジョークをいう習慣が違う点こそが問題になると考えられる。アラブ人は、日本人との笑い感覚に似ていて話の流れでジョークを言い、それをあらかじめ明確に知らせないのがユーモアの特徴の一つ。
また、アラブ人は聞いている相手に、冗談を語る合図を全く送らないわけではないが、「これからジョークを言いますよ」と言わなくても 、笑顔や声の動きなどで、相手に今言っていることが冗談であることを伝えるメカニズムがあるだろう。が、日本人の漫才と同じようにそれはノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニ ケーション)の面でもあり 、無意識なところも 多いと考えられる 。
一方、日本人は、アラブ人のようにいつも笑おうとしているわけではない。その意味で、日本人とアラブ人の笑感覚が異なるところもある。アラブ人のように上記に紹介したジョークによる作り話で日本人は笑う気になれないかもしれない。それはいかにも笑わせようとしていると伝わると引いてしまうからだ。そのため、日本人にとって、ダジャレやギャグは笑われるよりは馬鹿にされるものだと考える。そして、どちらかといえば、日本人はジョークのような作り話より本当にあったもしくは本当にあったようなことなら結構受ける。また、そのような笑ツボを狙って、落語や漫才などのように日本の笑芸人は、なるべく、本当らしく再現することで観客から笑いを引き出そうとする。まさに、「国民性も色々、お笑いも色々」といったところかな。









0 Comments
Hello. And Bye.
[url=https://google.com/aasgdhjhgasjfajsd#]google404[/url]
hjgklsjdfhgkjhdfkjghsdkjfgdh
thank you for your kind comment