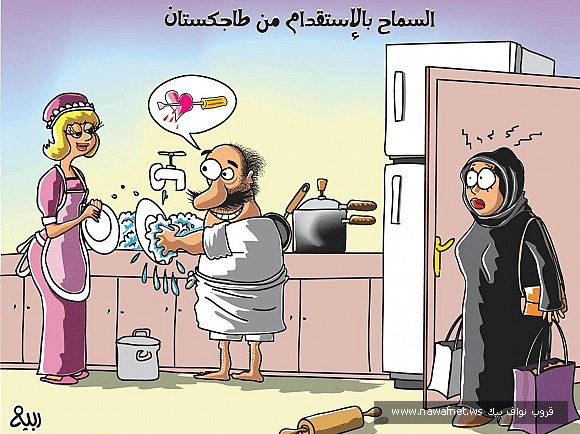アラブの世界、そこが知りたい! 人間関係の円滑剤、ユーモアのセンス!
アラブ人は、常に力を抜こうとする「弛緩志向」というマインドが得意。そして緊張を解消ためにも笑いやユーモアを生活によく取り入れるのだ。仕事など緊張のある一大事の時でもジョークを飛ばしたりユーモアのある表現を使うなどして気楽にしていられるのが「できる人」の証である。一方、日本人は、大切な場面になればますます力が抜けず表情も硬くなる「緊張志向」が目立つ。 アラブのトップリーダーや「できる人」は、どんなにせっぱ詰まった時でも、メンタルの強さや自信などを見せる証として冗談一つや二つ言えるゆとりをアピールする。 一方、日本人は、いつも力を入れて頑張っていなければならないのが美徳の一つだ。「生懸命やる」ことや「張り切る」ことはいいことで、力を抜くことは「不真面目」や「怠け」でよくないことである。そのため、日本では、冗談は真面目な姿勢に反するとの体育系的考えが支配 的である。そのためか、日本人にはあまりユーモアがないと思われているが 、日本には漫才や落語などの豊かなお笑い文化がある